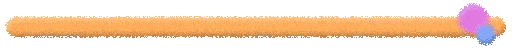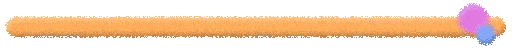| �j���j�N |
�j���j�N�ɏ�����������M������A�����I�ȗ͂������ƁA�A���V���Ƃ������������o����܂��B�j���j�N����������邽�߂ɍ��h�䕨���Ȃ̂ł����A����ɁA������̃v�����[�V�����i�K��}�������p�����邱�Ƃ������ŏؖ�����܂����B�܂��A�j���j�N�ɂ͓y��Ɋ܂܂��Z�����Ƃ����~�l���������ߍ��ނƂ�������������܂��B���̃Z����������\�h�����Ƃ��Ē��ڂ���Ă��܂��B����ɂЂƂ�����͂Ƃ肽�����̂ł��B
|
| ���b�L���E |
���b�L���E�Ɋ܂܂��T�|�j���Ƃ�������Ȑ����ƃC�\���N�G�`�Q�j���Ƃ����������A�x����y�є畆����̔������������铭�������邱�Ƃ������ɂ���ďؖ�����Ă��܂��B�܂��ŋ߁A�C�\���N�G�`�Q�j�����������𐮂��đ咰����̔�����}������Ƃ������Ƃ��킩��܂����B�P���ɂR���x�H�ׂ�����������ʂ͏\�����҂ł��܂����A�E�ۍ�p���������߁A�H�߂���ƈ݂Ɉ����̂ł��ꂮ������ӂ��Ă��������B
|
| �j���W�� |
�j���W���ɂ́A��-�J���`�����P�O�Og���V�R�O�O�P�ʁA�y�уr�^�~��A�EC�EE�@���@�S�P�O�OIU�A�Umg�A�O�D�Smg�@�Ƃ����Ղ�܂܂�Ă��܂��B�����͍R�_����p�ɗD��Ă���u�̂̓ŏ��������v�ł��B�܂��j���W���ɂ́A�w�~�Z�����[�X�ƃy�N�`���Ƃ����H���@�ۂ��L�x�ł��B�H���@�ۂ́A���b�ⓜ�����������Ƌz�������āA�C���X�����̋}�㏸���������܂��B�P�O�O��P�O�O���ȏ�����钰���ۂ̃G�T�ƂȂ��āA���̈��ʋۂ�ǂ��o���Ă���܂��B�_�`�_�̍ďz�𑣂��ė]���ȃR���X�e���[����r�o���A�����d����\�h���铭���A�X�|���W�̂悤�ɕې����ĕւ̃J�T�𑝂₵�āA�֔��咰�����h�����������ł��B
|
| �S�{�E |
�S�{�E�ɂ́A�H���@�ۂ��P�O�Og���ɂW�D�Tg�@���܂܂�܂��B���Ƀ��O�j���A�Z�����[�X�A�w�~�Z�����[�X�Ƃ������n���̐H���@�ۂ̓��������ڂ���܂��B���ɗn���Ȃ��H���@�ۂ͒��̌��N�Ɍ������Ȃ����̂ł��B�ւ̗ʂ��ӂ₷�ƂƂ��ɒ����h�����āA従��^���������ɂ��A�r�ւ��X���[�X�ɑ��i���Ă���邩��ł��B���ł����O�j���́A����̐���������Α����قǁA�ǂ�ǂ��Ă���s�v�c�ȐH���@�ۂł��B����́@�u���Q���O�j���v�Ƃ������̂ŏ������S�{�E�́A�����̐g���C�����邽�߂ɁA���O�j��������������o�����Ƃ��鐫����������ł��B���O�j���̓�������荂�߂邽�߂ɂ́A�u���`�I�j���v�ƂƂ��ɂƂ�̂��R�c�ł��B���`�I�j���͕K�{�A�~�m�_�̈���ŁA���E���E���E�����Ȃǂɑ����܂܂�܂��B�S�{�E�ƃ��`�I�j��
�̑����H�i�Ƃ����g�ݍ��킹���A���O�j�����ł������悭�Ƃ���H�ו��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
|
| �T�c�}�C�� |
�q�g�̎q�{�z����זE�ł���Hela�זE�ƁA�}�E�X�畆����̈�� B-16�@�זE��|�{���A����ɂ̓T�c�}�C���̍i��`�������A�����Е��ɂ͏���������������זE�����B���邩�ǂ������ώ@���܂����B���̌��ʁA�T�c�}�C���̍i��`���������ꍇ�A�����Ȃ������ꍇ�ɔ�ׂĂ���זE�̑��B���T���̂P�ȉ��ɗ}����ꂽ�̂ł��B���i�s����ƁA����זE�͕�����J��Ԃ��זE���������Ȃ邱�Ƃ��킩���Ă��܂����A�T�c�}�C���̍i��`�����������̂́A�זE���̂��̂��傫���Ȃ�A����ȍזE�̌`�ɖ߂��Ă��܂��܂����B�T�c�}�C���̍i��`�̂ǂ̐���������זE�̑��B��h���ł���̂����͂����Ƃ���K���O���I�V�h�Ƃ������������̓��������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�l�Ԃ��T�c�}�C����H�ׂāA�K���O���I�V�h��ێ悵�悤�Ƃ���Ȃ�A�̏d�U�OKg�Ŗ�Q�D�TKg�@�̃T�c�}�C�����K�v�ł��B�����\�h�̖ړI�Ȃ�Q�O�Og
���x�ŏ\���ł��B�܂��A�T�c�}�C���ɂ͐H���@�ۂ������܂܂�Ă��܂��̂ő咰����̗\�h�ɂ��Ȃ�܂��B
|
| �g�}�g |
�g�}�g�Ɋ܂܂�Ă��郊�R�s���Ƃ����Ԃ��F�f�����́A��-�J���`���̖�Q�{�Ƃ����ƂĂ������R�_����p�������Ƃ��킩��܂����B�^�o�R�̉��Ɋ܂܂���_�����f���W�J���́A�����̍��������_�f�ł����A������̑̓��Ŕ���������ƁA�זE���͎_�����זE�͎���ł����܂��B�Ƃ��낪��-�J���`�����ɗ^����ƍזE���̊����͂R���̂P���x�ɁA��-�J���`���̑���Ƀ��R�s������������ƍזE���͂W���̂P�ɂ܂ŗ}�����܂����B�܂��C�X���G���̃x���O���I����w�̌����ł́A���R�s���́A��-�J���`���̂P�O���̂P�̔Z�x�ŁA�x�̂���זE�̑��B��}������Ƃ���܂��B�g�}�g�������T�ɂP�O��ȏ�H�ׂ�l�́A�H�ׂȂ��l�ɔ�ׂāA��S�T��������ɂȂ�댯���͌����Ă����Ƃ�������������܂��B�P���ɐ��̃g�}�g��������傫�����̂��P�A�g�}�g�W���[�X�Ȃ�P�ʂƂ�̂�����̗\�h�ɂȂ�܂��B
|
| �z�E�����\�E |
�z�E�����\�E�ɂ́A��-�J���`���A�r�^�~�� C�EE ���L�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�l�͊F�����`�q�������Ă��܂����A���̂܂܂ł͉������܂���B������d�|�������u�C�j�V�G�[�^�[�v�����ƂȂ��������`�q�������ɓ��������`�q���������u�ُ�זE�v�ɕς��܂��B���̎��_�ł��܂�����̉肮�炢�̂��̂ł����A�����i�����i�v�����[�^�[�j���ُ�זE�ɓ����ƍזE���ɓŐ��̋��������_�f���������A��`�q�ُ̈�������N�����ُ�זE��{���̂���זE�Ɉ�ďグ��̂ł��B��-�J���`���͍R�_�������ł����̃��J�j�Y���̓r���Ŕ������銈���_�f����菜���܂��B����זE�̒a������O�őj�~����̂ł��B�܂��A����זE���ł��Ĕ��瑝�傷��ꍇ�ł��A�����_�f����|���Ȃ��炻�̕������B��}������ł����܂��B���̂�����-�J���`���ɂ͖Ɖu�זE�̐��Y�𑝂₵���̓��������������p������܂��B�����悭��-�J���`����ێ悷��Ȃ���Ƃ�������Ɏ��̂��x�X�g�B�y�������߂Ė��X�`�ɓ��ꂽ��V�`���[�Ȃǂ̏`���ɂ���Ɗܗʂ̖�U�O�`�V�O�����z���ł��܂��B��ł��ꍇ�ɂ͂قƂ�ǂ���ŏ`�ɗ���o�Ă��܂��̂Ō����̓_�ł͂��܂�悭����܂���B
|
| �L���x�c |
�������̓T�C�g�J�C���ƌĂ�Ă�����ʃ^���p�N���債�܂��B���̃T�C�g�J�C�����A����\�h�ɗL���ɓ����܂��B�T�C�g�J�C���͂P��ނ����ł͂Ȃ��A���ɐ���������A���̂ЂƂɁATNF
�i��ᇉ��q�j�Ƃ����̂�����܂��BTNF �����������瑽�����傳���قǁA����זE�����ł����铭���������Ȃ�Ƃ������Ƃ������܂��B�鋞���w���R�萳�������̎����ł������̖�̏`���}�E�X�Ɉ��܂��ATNF
���ǂ̂��炢����Ă��邩�ׂ܂����B���̌��ʁA�����������܂����}�E�X�ɂ���ׁA�L���x�c�A�i�X�A�_�C�R���Ƃ������W�F��̏`�����܂����}�E�X�́ATNF
�̊�������P�O�{�ɂ��Ȃ�܂����B���ꂾ������זE����菜���͂������Ƃ������Ƃł��B���������̊����́A�j���W����s�[�}���Ȃǂ̗Ή��F��������邱�Ƃ��킩��܂����B����\�h�ɂȂ��Ƃ��Ďv�����̂͗Ή��F��ł����A�������̓����ōl����ƁA�W�F�������̗\�h�ɗL���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B
|
| �}�C�^�P |
�}�C�^�P�́A�q�_�i�V�^�P�ڃT���m�R�V�J�P�Ȃɑ����܂����A�����q�_�i�V�^�P�ڂ̃J�����^�P���璊�o���ꂽ��-D-�O���J���ƌĂ�鑽���́i�u�h�E������������A�Ȃ��������q�����j�́A����̖Ɖu�Ö@�܂Ƃ��ėՏ��ɍL�����p����Ă��܂��i�N���X�`���Ƃ����܂��j�B��œ����A����\�h�̎�ƂȂ鐬���͐��n���̃�-D-�O���J���ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���n����-D-�O���J���̓}�C�^�P�ɂ�����܂����A�}�C�^�P�̏ꍇ�ɂ̓�-D-�O���J��������ς����ƌ������A���ɗn���Ȃ��u���s�n�������́v�Ƃ����`�łP�O�`�R�O�����܂܂�Ă���̂������Ȃ̂ł��B�T���R�[�}�P�W�O�Ƃ�������זE���}�E�X�ɈڐA���܂����B���ʂȂ�T�`�U�T�ԂŎ���ł��܂��܂��B������ڐA�������ォ��}�C�^�P�̐��s�n�������̂��P��ɑ̏d�PKg������P�Omg�A���͂P�O�Omg�C�P�������ɒ��˂����}�E�X�́A�����������̑��B���}������܂����B���˂����ł͂Ȃ��G�T�ɍ����ĐH�ׂ������ꍇ�ɂ��A�}�C�^�P�̐��s�n�������͓̂��l�̍R�����p���������Ƃ����炩�ɂ���Ă��܂��B�����Ƀp�C�G���Ƃ����Ɖu�튯������܂��B�p�C�G���́A�Ɖu�������ǂ郊���p����}�N���t�@�[�W�Ȃǂ̖Ɖu�זE�̂��܂��ŁA�N�������ٕ���������ƁA�����̖Ɖu�זE���H�ׂĂ��܂��܂��B�}�C�^�P�̐��s�n�������̂́A�p�C�G���ɑҋ@���Ă���Ɖu�זE���h�����܂��B�h�����ꂽ�Ɖu�זE���A�̓��ł���זE���ٕ��Ƃ��čU��������̂ƍl�����܂��B
|
| �V���W |
�������w�����r��N�Y�搶�̎����ŁA�V�Q�C�̃}�E�X���̂Q�Q�ɕ����AA�Q�ɂ͕��ʂ̃G�T���AB�Q�ɂ͕����ɂ����V���W���T��������������^���Ď���A�P�T�Ԍ�ɂ��ׂẴ}�E�X�ɋ��͂Ȕ�����܂�牺���˂��ĂP�N���ɂ킽���Čo�߂��ώ@���܂����B���ʂ́AA�Q�ł͂P�U�T��ɍŏ��̂P�C�ɂ��ł��A�V�U�T�Ōv�Q�P�C�ɔ����݂��܂����B����V���W��H�ׂ�B�Q�ł��ł����̂͂V�U�T��ʂ��Ă킸���R�C�A�����͂V���̂P�ɗ}����ꂽ�̂ł��B����זE�̂��́A�t���[���W�J���ƌĂ�镨������`�q�▌���_�����邱�Ƃň����N������܂��B�}�E�X�ɃV���W���P�O���܂ރG�T���Q�U���ԗ^�������ƁA���t���Ƃ��Ē��ׂ��Ƃ���A�t���[���W�J����⑫���銈�������܂��Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B���t���Ńt���[���W�J����⑫���銈�������́A���t���̂����̍����q�̃^���p�N���ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�V���W�ɂ́A����זE�̑��B��}�����p�����邱�Ƃ��������Ă��܂����B������ڐA�����}�E�X���A�@���ʂ̃G�T�A�A����Ԃ����V���W���������G�T�A�B�V���W���A�~���[�[�i���t�ȂǂɊ܂܂������y�f�j�ŏ����������̂��������G�T�A�̂R�ɕ����A�P�W����ɂ���̏d�����r���܂����B���ʂ͇@�ɂ���ׁA����̑��B���A�łS�W���A�B�ł͂U�O�����j�~���ꂽ�̂ł��B���̂��B�}����p�́A�V���W�Ɋ܂܂�鑽���́i�����A�Ȃ��������j�A���͓��^���p�N�����̖̂Ɖu�זE�����邱�Ƃł����炳�ꂽ���̂ƍl�����܂��B
|
| �G�m�L�^�P |
���쌧���̃G�m�L�^�P�͔|�ƒ�A�S�Q�O�O�O�ˈȏ��Ώۂɂ��S���ׂ��Ƃ���A���S�̂̎��S�������R�X�����Ⴂ���Ƃ����������������ʂ�����܂��B����ɃG�m�L�^�P��p�ɂɐH�ׂ�ƒ�قǂ���Ŏ��S����댯�x�͌���܂��B�G�m�L�^�P������قǂ̂���}�����ʂ�����v���́A�u
EA�U �v�Ƃ������^���p�N�ɂ���܂��BEA�U�́A���V�O���A�^���p�N���R�O������\������镨���ł��B����
EA�U���}�E�X�Ɉ��܂���ƁA�^�����ʂɔ�Ⴕ�Ă���̑��B���h����̂ł��B�}�E�X�̑̏d�PKg�ɑ��āA�P�Omg ��
EA �U���P�O���ԓ��^����Ƃ���̑��B�͂P�Q���}������܂��B�T�O�����ł͂R�X���A�P�T�O�����ł͂T�X�������B��j�~���܂����B���������˂����Ă����ʂ͂قƂ�ǂȂ��A������ێ悵�ď��߂āAEA
�U�͂��̍R�����p�������̂ł��BEA�U������זE�ڍU������̂ł͂Ȃ��A���̖̂Ɖu�זE�������������邱�ƂŁA����זE�̑��B��h�����Ƃ��m�F����܂����B�G�m�L�^�P�ɂ͊����_�f�̊�����}����R�_����p������܂��B�قƂ�ǂ̐H�p���̂��ނɍR�_����p������܂����A�G�m�L�^�P�̍�p�����͂ł��邱�Ƃ͎����ł��m�F�ς݂ł��B
|
| �J���t�����[ |
�H�ו��Ɋ܂܂�镨���Ȃǂł����}���邱�Ƃ��A����̉��w�\�h�Ƃ����܂��B�ŋߒ��ڂ���Ă��鉻�w�\�h�����ɁA�A�u���i�Ȃ̖�i�J���t�����[�A�u���b�R���[�A�L���x�c�Ȃǁj�Ɋ܂܂��C�I�E������������܂��B��w��w�������̐X�G���搶�̎����ŁA�J���t�����[���璊�o���ꂽMMTS�i���`�����T�l�T�C�I�X���z�l�[�g�j�Ƃ����C�I�E���������A���b�g�ɗ^��������������܂��B���b�g�̏����́A���̂S�Q�ł��B
A�Q�������܁{���ʂ̃G�T
B�Q�������܁{MMTS���Q�Oppm�Z�x�ō������G�T
C�Q�������܁{MMTS���P�O�Oppm�Z�x�ō������G�T
D�Q�����ʂ̃G�T�̂��@�@
A�`C�Q�̔����܂́A�咰����������N�������̂ŁA�T�P��v�R��A�牺���˂��܂����BA�Q��D�Q�ɂ͕��ʂ̃G�T���AB�Q��C�Q�ɂ͔����܂̓��^�I����AMMTS���Q�Oppm�A�P�O�Oppm�̔Z�x���������G�T��^���A�X������ɁA���b�g�̒��ׂĂ݂܂����B���ʁA���ʂ̃G�T��H�ׂ�A�Q�ł͂S�R���̔����ł������AMMTS���Q�Oppm������B�Q�ł͔����͂Q�T���ɁAMMTS���P�O�Oppm������C�Q�ł́A�P�C�����ł����A�������S����������ꂽ�̂ł��B�܂�MMTS�́A����זE�̑��B���}�������B��̎�����Ƀ��b�g�̑咰�S���ׂ��Ƃ���A�����܂̎h�����Ȃ�D�Q�ł́A�זE�S�̂ɐ�߂镪�������זE�̔䗦�͂Q�D�T���ɂ����܂���ł������A�����܂Ŏh������A�Q�ł́A�P�R�D�U���ƍזE�̑��B���i��ł��܂����B�Ƃ��낪�A�����ܓ��^���MMTS��^����B�Q��C�Q�ł́A���ꂼ��S�D�T���A�R�D�S�����זE�̑��B���������}�����A�����܂̎h�����Ȃ�D�Q���x���������Ă��܂����B�܂��AMMTS�́A�咰����݂̂Ȃ炸�A�̑����̔������}���邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A���݁A�x����ȂǑ��̑���ɂ��Ă��������i�߂��Ă��܂��B
|
| �u���b�R���[ |
�����ł́u �H�� �v�Ƃ����āA�Â����犿���̑f�ނƂ��ė��p����Ă��܂����B���{�Ƀu���b�R���[�̐l�C���蒅�����̂́A�H���@�ہA�r�^�~���A�~�l�������L�x�ŁA���Ƀr�^�~��C�ƃr�^�~��A
�A�J���V�E���A�S�ɕx��ł��邱�Ƃ��m��ꂽ����ł��B�J���`�����r�^�~��C���A���\�h�ɗL���ȉh�{�f�Ƃ��āA���܂�ɂ��L���ł����A�������A�u���b�R���[�̔�����}�����ʂ̖{�̂́A�t���{�m�[���̈��ł���u�P���Z�`���v�̑��݂ɂ���܂��B�J���`���A�r�^�~��C�A�P���Z�`���̂R�̕����́A�����_�f�̓�����}������Ŕ������}������R����\�h�����Ȃ̂ł��B�܂��A�����J�ł́A�u���b�R���[�Ɋ܂܂�Ă���u�X���z���t�@���v�ɁA������}�����ʂ�����ƔF�߂��Ă��܂��B�X���z���t�@���́A�r�^�~��C�Ƃ͈���ĔM�ɋ����A�d�q�����W����M�ɂ�钲�������Ă��������j��܂���B���q���q�勳�������F���搶�̎����ɂ��ƁA�Q�T�C�̃��b�g��DMBA�Ƃ������������𓊗^���A�ʂ̂R�X�C�ɂ͔��������ƂƂ��ɃX���z���t�@����^���܂����B���̌��ʁA������������^����ꂽ�O���[�v�ł͂U�W���ɓ����ł����̂ɑ��āA�X���z���t�@����^�����O���[�v�ł͓�����̔��ǂ͂Q�U���ɂ����܂���ł����B�X���z���t�@���́A�H�ׂĐ����Ԃō�p����Ƃ����Ă��܂��B�܂��A�u���b�R���[�̒��ɑ��݂��Ă��邠���̍y�f���X���z���t�@���ɍ�p���āA����ɔ�����}�����ʂ����܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ�����������܂��B����\�h�H�Ƃ��ėL�����p��������̂ЂƂł��B
|
| �A�V�^�o |
�V�N�ȃA�V�^�o�̌s��܂�Ɖ��F���`���o�Ă��܂������ꂱ�����ł����ڂ��ׂ�����\�h�����̃J���R���ŁA�A�V�^�o�ŗL�̐����Ȃ̂ł��B������ȑ�w�������R�O�搶�̎����ɂ��ƁA�x�̔�����ɂ��Ă݂��}�E�X�����ŁA������������^�����P�[�X�ł́A�P�Q�C�����ςS�D�X�C�ɂX�P�D�V�̎�ᇂ��������܂������A�������ɃA�V�^�o�̕�����������ƁA�P�Q�C���A��ᇂ����������}�E�X�͕��ςP�D�R�C�Ɍ������܂����B��ᇌ��ɂ��Ă��A�U�U�D�V�ɗ}�����錋�ʂƂȂ�܂����B�x����ȊO�ɁA�畆�Ƒ咰�̔�����ɂ��Ă��������܂������A��������}������Ƃ������ʂ��łĂ��܂��B�זE��������ɂ̓C�j�V�G�[�V�����ƃv�����[�V�����Ƃ����Q�̒i�K���o��킯�ł����A�A�V�^�o�Ɋ܂܂��J���R���ɂ́A�v�����[�V�����i�K�ɍ�p���āA�זE�̂���}�����铭��������̂ł��B�܂��A�V�^�o�ɂ́A�N�}�����Ƃ����������܂܂�Ă��܂��B������J���L�����l�ɂ���\�h�Ɍ��ʂ������Ƃ������Ƃ��킩���Ă��Ă��܂��B���̑��ɂ���-�J���`����r�^�~��C�Ȃǂ��L�x�ł��B
|
| �Z���� |
�Z�������H�p�Ƃ��č͔|�����悤�ɂȂ����̂̓t�����X�����߂ĂŁA�P�V���I�̂��Ƃł��B���̏L�݂������̂ɗp�����܂����B���{�ɓ`������̂́A�퍑����ɉ������������N���玝���A�����Ƃ���܂��B����䂦�A�Z�����̂��Ƃ𐴐��l�Q�Ƃ������܂��B�Z�����ɂ́A�R�����ÏW��p�����邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă��܂��B�R�����ÏW��p�Ƃ́A���ǂ̒��Ō��t���ł܂�ɂ������A�������ł���̂�h�������ŁA�S�؍[�ǂ�]�[�ǂȂǂ̗\�h�ɖ𗧂��܂��B�����M��w�̎R�����O�搶��́A���낢��ȐH�i�ɂ��āA�R�����ÏW��p�ׂĂ��܂����A���̒��ŁA�Z�����͂��̍�p����ԋ������̂̂ЂƂɂ����Ă��܂��B |
| �����S |
�咰�ɂ͂P�O�O��ށA�P�O�O�����̍ۂ����݂��A���_�ہi�r�t�B�Y�X�ۂȂǁj�ƕ��s�ہi�咰�ۂȂǁj�����͑��������Ă��܂����A���̃o�����X��傫�����E����̂��H�����ł��B���s�ۂ̃G�T�́A���Ȃǂ̐H�׃J�X���܂܂��^���p�N���ł����A���_�ۂ͐H���@�ۂȂǂ̓������D���Ƃ��Ă���̂ł��B�����Ƃ肷����Β����ɕ��s�ۂ��͂т���A�H���@�ۂ�L�x�ɂƂ�A���_�ۂ��ӂ����s�ۂ��ɐB���ɂ������������̂ł��B�Ƃ��Ƀ����S�Ȃǂ̉ʕ��Ɋ܂܂��y�N�`���Ƃ����H���@�ۂ́A���ꎩ�̂����s�ۂ̐����}���鋭�͂ȐËۍ�p�������Ă��܂��B�x�R��Ȗ�ȑ�w�����̓c�V�����搶�̎����ł����A���b�g���R�̃O���[�v�ɕ����AA�Q�ɂ͕��ʂ̃G�T���AB�Q�ɂ̓I�����W�̃y�N�`�����Q�O���܂ރG�T���AC�Q�ɂ̓����S�̃y�N�`�����Q�O���܂ރG�T��^���Ȃ���A�咰����̗U���܂��T�P��A�v�P�O��ɂ킽���Ē��˂��܂����B�����܂̒��˂��͂��߂ĂR�O�T��Ƀ��b�g�̒��ׂĂ݂�ƁAA�Q�ł͂W�R���ɑ咰���ł��Ă����̂ɑ��āA�a�Q�ł͂T�T���ɂ��������܂����B�����S�̃y�N�`����H�ׂ��b�Q�ł͂���ɒႭ�A����̔������R�W���ɂ��������܂����B����̓y�N�`���̐ێ�ʂɂ���ē��_�ۂ����������Ƃ̌��ʂł��B�܂��A�咰�ɗ���Ă������������́A���ǂ̔S�����h�����Ă����U������ƁA�ꕔ�͋z������Č��t���ɓ���̑��֑����A�O���N�����_�̓����ŃO���N�����_�����̂Ƃ������Q�ȕ����ɕς����܂��B���̕����́A�_�`�Ƃ�������ɏ\��w���ɔr������A�咰��ʉ߂��ĕւƂ�������ɔr������܂��B�Ƃ��낪�����ɕ��s�ۂ������ƃ�-�O���N���j�_�[�[�Ƃ����y�f����薳�Q�̃O���N�����_�����̂��Ăє��������ɂ��Ă��܂��A�������̈ꕔ���Ăђ��ǂ���z������Ċ̑��ւ����A�z���邱�ƂɂȂ�܂��B��̎����Ń�-�O���N���j�_�[�[���֒��ɂǂꂭ�炢�܂܂�Ă��邩���肵���Ƃ���A���ʂ̃G�T��H�ׂ����b�g�ɂ���ׁA�����S�̃y�N�`����H�ׂ����b�g�̒����ł́A��-�O���N���j�_�[�[�̊������P�O���ɂ܂Œቺ���Ă���̂��m�F����܂����B����ɂP�̃����S�ł����h���������̂ł��B
|
| �o�i�i |
���a�R�O�N��܂ł́A�����ŋM�d�ȉʕ��������o�i�i�́A���ł͎育��Ȓl�i�Ŕ����܂��B�o�i�i�́A�������̓��������߂ĖƉu�͂����邱�Ƃ������ŏؖ�����܂����B�鋞��w�����R�萳���搶�̎����ł����A�}�E�X�Ƀo�i�i�ʏ`�o���ɐڎ킷����������A�}�N���t�@�[�W�i��H�זE�j�A�����p���̂��ׂĂ̗ʂ����������Ƃ��m�F����܂����B�}�N���t�@�[�W�́A�T�C�g�J�C�������o���܂����A���̃T�C�g�J�C���̒��ł��d�v�Ȃs�m�e�i��ᇉ��q�j�́A�}�N���t�@�[�W������זE���E�����ɂ͕K��������܂��B�ǂ�Ȃ��̂��s�m�e�𑽂���邩���ׂ��Ƃ���A�Ƃ��Ƀo�i�i�̌��ʂ�������Ă��܂����B�܂�����זE�Ƀo�i�i�ʏ`�𒍎˂����Ƃ���A��ᇂ��傫���Ȃ�ɂ������Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�l�Ԃ̗͑͂��Ȃ��Ƃ��Ƀo�i�i��H�ׂĂ��܂������A�̌��I�ɒm���Ă�������ł��傤�B
|
| ������ |
�u��������Ă������A�Ă�Ղ��{�̂���g���Ȃǂ̗g�����ɂł����R�Q�͂���̂��ƂɂȂ�v�Ƃ������Ƃ͂悭���ɂ��܂����A�R�Q�ɂ͑̂̒��ɓ���Ɣ������������o���g�t���[���W�J���h�������܂܂�Ă��܂��B�������̓t���[���W�J�������܂��Ĉ��肵�������ɕς��Ă��܂��̂ł��B�t���[���W�J���́A�E�ۂ�Ɖu�����߂�Ȃǂ悢����������ꍇ������܂����A�זE����זE���̂c�m�`����������ƓŐ��������ꍇ������܂��B�l�Ԃ̑̂̒��ɂ͂����}���镨��������̂ł����A�r�n�c�i�X�[�p�[�E�I�L�V�h�E�f�B�X���_�[�[�j�Ƃ����y�f�͂��̑�\�ŁA���炾�̒��ɂr�n�c����������A���������t���[���W�J���������Č��N�ȑ̂�ۂ��Ƃ��ł��܂��B�������A��C�␅�A�H�ו��ɂ��t���[���W�J���͑��݂��Ă��܂��B�����͎_�f���֗^���Ă��邽�ߊ����_�f�ƌĂ�Ă��܂����t���[���W�J���̈��ł��B�t���[���W�J���������Ă����Ȃǂ̃R�Q��H�ׂ���A�X�g���X��a�C�ő̂̋@�\���ቺ���Ă��A�t���[���W�J���͑������Ă��܂��A�̓��̂r�n�c�����ł͑Ή�������܂���B���������ă������Ȃǂ̃t���[���W�J����}���铭�������H�i��H�ׂ邱�Ƃŕ₤�K�v������̂ł��B
|
| �C���V |
�C���V�̎��Ɋ܂܂��̂��A�h�R�T�w�L�T�G���_�A���Ȃ킿�c�g�`�ŁA�����悭�Ȃ鐬���Ƃ��Ęb��ɂȂ������Ƃ�����܂����B�ŋ߂̌����ł͑咰�A�����A�x�A�̑��A�O���B�A���B�Ȃǂ̏�����n�Ɛ��B��̂���\�h�ƁA�]�ڂ�h�����Ƃ��킩���Ă��܂����B�݂���ɂ͂��܂�����Ȃ��悤�ł��B�c�g�`���݂ɂƂǂ܂鎞�Ԃ��Z�����Ƃ��A���R�̈�ɍl�����܂��B�w�̋��ɂc�g�`�ܗL�ʂ͑����A�܂��A�ڂ̌��̎��b�ɑ����܂܂�Ă��邽�߁A�ۂ��ƂP���H�ׂ���C���V�͍œK�ȐH�ނƂ����܂��B�A�������b�̃��m�[���_�́A�̓��ɓ���ƁA��-���m�����_�A�A���L�h���_�ւƕω����A�ŏI�I�ɂ̓v���X�^�O�����f�B��
�d 2�Ƃ���������v�����[�^�[�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�A���L�h���_���ω�����ۂɂ��������̍y�f����p���܂����A�c�g�`�͂����̍y�f��}�����A�v���X�^�O�����f�B���d2�����Ȃ��悤�ɓ����̂ł��B���m�[���_���̂��̂͑̂ɕK�v�ȕ����ł����A�哤��ĂȂǐA�����H�i�̂قƂ�ǂɊ܂܂�邽�߁A�ǂ����Ă��ߏ�ێ�ɂȂ肪���ł��B�܂����ނɂ́A�A���L�h���_���܂܂�Ă���̂ŁA�����p�ɂɐH�ׂ�l�͂���ɂȂ�댯���������Ƃ��킴�����������B����ȍזE��50�炢����Ƃ���ȏ㕪���זE�����玀�ɂ܂��B������A�|�g�[�V�X�Ƃ����܂���������E�̓A�|�g�[�V�X��Y��Ė����ɕ���̂ł��B�������c�g�`�ɂ͂���זE�ɂ��̃A�|�g�[�V�X���v���o�������p������������Ƃ������Ƃ��A�啪��ȑ�w�̌����ł킩���Ă��܂����B����̓g�s�b�N�X�ł��B�c�g�`������100���Ƃ��̂͐��̎h�g�A�ς���Ă����肷���80���ɗ����܂��B�t���C��50����60���c�g�`�����܂��B
|
| �R���u |
�R���u�̃k���k���ɂ́A�t�R�C�_���Ƃ��������ނ��܂܂�Ă��܂��B�R���u�ɂ́AF �� U �̂Q��ނ̃t�R�C�_�����q�����݂��܂����A���̂���U�|�t�R�C�_�����q�̂ق����A����זE�����E�ɒǂ����܂��B��o�C�I����������������V�i�搶�̎����ɂ��ƁA�R���u���璊�o����U�|�t�R�C�_�����PL������P���Z�x�̉t�̂ɂ��A�������זE��P������ꂽ�V���[���ɓ��ꂽ�Ƃ���A�Q�S���Ԍ�ɂ͂���זE�͔����A�V�Q���Ԍ�ɂ͂قڃ[���ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł��B�����������a�זE��A�݂���זE�̎����ł����l�̌��ʂ�����ꂽ�����ł��B���ڂ��ׂ����Ƃ́A����זE�������DNA�����y�f�ɂ���Ď��E�������ƂŁA����זE�ɂ́A�قƂ�ǂȂ�̉e�����݂��Ȃ��������Ƃł��BU-�t�R�C�_���̓R���u�����̂܂ܐH�ׂĂ������ʂ����҂��邱�Ƃ��ł��܂��B
|
| ���J�� |
�E���J���ɂ́A���[�h���܂܂�Ă��܂��B���É���w��Q�O�ȏM���[�b�搶�̎����ł����A�l�Y�~�ɓ�������������R�O���[�v�ɕ����Ă������Ă���̑��B�����݂����̂�����܂��B�G�T�̓��e�́A�@���ʂ̃G�T�����̂��́A�Q���̕������J�����������G�T�A�B�T���̕������J�����������G�T�Ƃ������̂ł��B���ʂ́A�@�̃O���[�v�̂��傫���Ȃ����̂ɑ��A�B�̃O���[�v�̂���́A�قƂ�Ǒ��B���܂���ł����B�܂��A�����ׂ����ƂɁA�A�̃O���[�v�̂�����قƂ�Ǖς��Ȃ��܂܂������̂ł��B�܂肦���̂P���̗ʂ̃��J���ł��A�\���Ȍ��ʂ��������̂ł��B����́A���[�h�ɂ͈�x�ł�������זE�����E�i������A�|�g�[�V�X�Ƃ����j�ɒǂ����ޓ��������邩��ł��B���������J���𑽂��Ƃ�Ƃ�قǁA���t���̃��[�h�̗ʂ͑����Ȃ�܂��B�܂�A���J���̃��[�h�́A���t�ɋz�������Ɠ�����̑g�D�܂ł��ǂ���A����זE�����E��������ʂ�����̂ł��B�܂����J���̃��[�h�ɂ́A������\�h�̌��ʂ����邱�Ƃ��A�l�Y�~�̎����Ŋm���߂��Ă��܂��B
|
| ���[�O���g |
���{�l�ɂƂ��Ă͂����������I�ȐH�ו��ɂȂ������[�O���g�ł����A���͗L�j�ȑO�������Ă������E�ŌÂ̐H�ו��̂ЂƂȂ̂ł��B���������ӂ�����ɂ��Ă�����̂́A��������_�ۂŔ��y���������̂ł��B�l�Ԃ̒��̒��ɂ́A�A��P�O�O��ނ̒����ۂ����݂��Ă��܂��B���̒��ɂ́A���N�ێ��ɖ𗧂P�ʋۂƁA�L�Q�Ȉ��ʋۂƂ�����܂��B���_�ۂɂ͒��̒��̑P�ʋۂ𑝂₵�Ĉ��ʋۂ����炷����������܂��B�������P�ʋۂ͒��̓����𐮂��A�֔�≺����h���̂͂������A���̒��̗L�Q�����̓�����}��������A�r���𑣂����肵�āA���̂��ł���̂�h���̂ł��B�܂��A���[�O���g�̓��_�ۂɂ͍R�ψٌ�����p�����邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B�זE��DNA�ɓˑR�ψق��N�������镨�����u�ψٌ��������v�Ƃ����܂��B�ψٌ��������́A�Ƃ��Ƃ��Ă���זE������܂��B���̕ψٌ��������̐����⓭����}�����p���A�R�ψٌ�����p�Ƃ����܂��B�M�B��w�_�w���ז얾�`�搶�̎����ł����A���[�O���g�P�O�O�����H��ɂR��A�P�T�ԐH�ׂĂ��炢�A���̐l�����֒̕��ɔ����������ǂꂭ�炢�c���Ă��邩���ׂ܂����B����ƁA�V�`�W���̐l�֒̕��̔��������͌������Ă��܂����B����͔��������̕ψٌ������A���[�O���g�̓��_�ۂɂ���ė}����ꂽ���Ƃɂ��܂��B�ʂ̎����ł́A����זE����A�����}�E�X�Ƀ��[�O���g��^�����Ƃ���A���ʂ̂�����^�����}�E�X���A����זE�̑��B���}����ꂽ���Ƃ��m�F����܂����B���̒��ɂ́A����זE���������Ă���P�[�X�����������A�Ƃ���������܂��B����ɁA���_�ۂɂ͑̓��ł���זE���U������זE�i�L���[T�זE�A�i�`�������L���[�זE�AB�זE�Ȃǁj�𑽂���点�āA����זE�̑��B��}������ʂ�����܂��B
|
| �J���[�� |
�J���[���Ɍ������Ȃ��^�[�����b�N�B����̓E�R�����������������̂ł��B�^�[�����b�N�̎听���́A�N���N�~���Ƃ������F�̐F�f�ŃJ���[�̃��[�����F���̂́A���̃N���N�~����L�x�Ɋ܂�ł��邽�߂ł��B�N���N�~�����̂��̂̍R�_����p�͂��قNj�������܂��A�ێ悵���N���N�~����������z�������ہA�S���̍זE���̍y�f�ɂ���āA�e�g���q�h���N���N�~���Ƃ������͂ȍR�_�������ɕϊ�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�܂�J���[���C�X��H�ׂ�A�N���N�~�������ǔS���Ńe�g���q�h���N���N�~���ɂȂ�A���͂ȍR�_����p�����ăt���[���W�J���ɂ��_���̊Q��h���ł����\�����傢�ɂ���Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ȃN���N�~���̑�Ӄ��[�g���猩�āA�܂����҂����̂��咰����̗\�h�ł��B�咰����������N���������������}�E�X�ɗ^���A�R������ɒ��ׂ�ƁA�����������O���a�ς����������ɔF�߂��܂��B
��������Z���^�[�Ɩ��É���w�̋��������ł́A�e�g���q�h���N���N�~�����O�D�T���܂ނ�����^�����}�E�X�́A���ʂ̂�����H�ׂ��}�E�X�ɂ���ׁA�咰�̑O���a�ς̔�������R�O�����}�����܂����B�N���N�~�����O�D�T���܂ނ�����^�����ꍇ�ł��A��P�R���̗}�����F�߂��A����̓N���N�~���̈ꕔ���咰�Ńe�g���q�h���N���N�~���ɑ�ӂ���A�R�_����p���������ʂƍl�����܂��B�N���N�~���̐ێ�͑咰����݂̂Ȃ炸�A���̑����g�D�ł�����\�h�ɖ𗧂��Ă����\��������܂��B�A�����J�ł̕ɂ��A�N���N�~���̐ێ�Ŕ畆����̔������}����ꂽ�Ƃ��Ă��܂��B�J���[���C�X�͍��⍑���I�ȃ��j���[�̂ЂƂƂ��Đe���܂�Ă��܂����A�J���[�̋�ƂȂ�j���W���̓J���`�����A�W���K�C���͔M�ɋ������肵���`�Ńr�^�~���b���܂݁A���C�X�̓r�^�~���d�̏d�v�Ȑێ挹�ł��B�܂�J���[���C�X��H�ׂ�A�N���N�~���̂ق��ɂ����R��ނ̍R�_���r�^�~�����Ɏ�邱�ƂɂȂ�A����\�h�ɑ�����ʂ����҂����̂ł��B
|
| �S�} |
��-�J���`����r�^�~���d�͍זE���ɑ��݂��A�t���[���W�J���̍U���@����זE������Ă��܂����A�זE���ł�����ނ̍y�f�������Ă��܂��B���̈��ł���O���^�`�I���y���I�L�V�_�[�[�̍\�������Ƃ��Č������Ȃ��̂����ʌ��f�E�Z�����ł��B�Z�����́A�A���ł̓S�}�ɖL�x�Ɋ܂܂�A�P�O���̃S�}�Ŗ�T�R�ʂ��̃Z�������Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�S�}�ɂ̓Z�T�~�m�[���Ƃ����S�}���L�̍R�_���������܂܂�Ă��܂��B�Z�T�~�m�[���͂��ܖ��Ɋ܂܂�邾���łȂ��A�S�}��H�ׂ�ƁA�����ۂ̓����Œ��Ǔ��ŃZ�T�~�m�[�����������܂��B�z�����ꂽ�Z�T�~�m�[���͌��t�ɂ���đS�g�̍זE�ɉ^��A���̍R�_����p�Ńt���[���W�J���̍U������זE������Ă���܂��B�זE�̒��̈�`�q���t���[���W�J���ɂ���Ď_�������ƁA���̏����C�������ߒ��łW-�n�g���f�i�W�|�q�h���L�V�f�I�L�V�O�A�m�V���j�Ƃ����������A���ɑ����܂��B�܂�A�W-�n�g���f�͑̓��ň�`�q���ǂꂾ���_������A���������Ă��邩�������w�W�Ƃ����܂��B���ʂ̏�Ԃł��A�זE���ł͈�`�q�̑����ƏC�����J��Ԃ���Ă��邽�߁A���b�g�̔A�ׂ�ƂW-�n�g���f�����o����܂��B�������Z�T�~�m�[����^����ƁA�W-�n�g���f�ʂ��������܂����B���b�g�Ɏl�����Y�f�Ƃ����ア����������^����ƁA���̎h���ő�ʂ̃t���[���W�J�����̓��ɔ������邽�߁A�W-�n�g���f�̔A���̔r���ʂ������܂��B�������A������Z�T�~�m�[����^���邱�Ƃŗ}�����܂����B�S�}��H�ׂ�A�Z�T�~�m�[�����̓��ōR�_����p�����čזE�̂���h���ł����\�������̎����͎����Ă��܂��B
|
| �݂� |
����������Z���^�[�������u�w�����E���R�Y���m�̍s���������ŁA�݂��`�����ސl�́A�قƂ�Lj��܂Ȃ��l�ɔ�ׂĈ݂���Ŏ��ʐl�����Ȃ��Ƃ����f�[�^���łĂ��܂��B���̂悤�ȉu�w�I�����ɂ���āA�~�\������̔��������������邱�Ƃ͂��łɖ��炩�ɂȂ��Ă��܂��B���̂ЂƂ�������̎����ł��B�L����w�������˔\��w�������E�ɓ����O�搶�̎����ɂ��ƁA���b�g�ɔ�������^���Đl�H�I�ɓ���������A������ȉ��̂S�̃G�T��^�����O���[�v�ɕ����A�����ɂɂ��Ĕ�r�������̂�����܂�
�@�@�@�@�@�@�@�`�@�Q�F���ʂ̃G�T�@
�@�@�@�@�@�@�@�a�@�Q�F���ʂ̃G�T�{�~�\�@
�@�@�@�@�@�@�@�b�@�Q�F�R�z��������
�@�@�@�@�@�@�@�c�@�Q�F�R�z�������܁{�~�\�@
�@���ʂ́A�a�Q�ł́A�`�Q�ɔ�ׂĔ����������Ɖ�����܂����B�����Ă��̒l�́A�R�z�������܂�^����C�Q�ɕC�G����قǂ������̂ł��B�R�z�������܂ƃ~�\�p����D�Q�ł́A���̌��ʂ͂���ɑ����A�قڊ��S�ɓ�����̔������}����ꂽ�قǂł����B�~�\�Ɋ܂܂�鐬���́A�ǂ���Ƃ��Ă��̂ɂ������̂���ł����A����\�h�ɖ𗧂��Ă�����̂́A�t���{�m�C�h�ł��B�̑�����̈�`�q�����}�E�X��p���������ł́A���ʂ̃G�T�A�~�\���������G�T�A�t���{�m�C�h���������G�T�̂R��ނŔ������r���܂����B���̌��ʁA���ʂ̂�����^�����}�E�X�ɔ�ׁA�~�\��t���{�m�C�h���������ꍇ�ł́A�������啝�ɗ}�����܂����B�ʂ̓�����̎����ŁA����̔����������Ă݂�ƁA���ʂ̃G�T�ł͕��ςS�̂����ᇂ��ł����̂ɑ��A�~�\���������G�T�ł͂Q�A�t���{�m�C�h���������G�T�ł͂R�̂����ᇂ��ł���Ƃ������ʂ������܂����B�����̎������ʂ���A�m���ɂ���\�h�̎���̓t���{�m�C�h�ł��邱�Ƃ��킩��܂����A������ꂾ���ł͂���܂���B���Ƃ��~�\�Ɋ܂܂�Ă���y��A���_�ۂȂǂ́A�̓��ō�������锭�������̏����ɖ𗧂��Ă���Ƃ̕�����܂��B�܂�t���{�m�C�h�𒆐S�ɁA�������̐��������悳��邱�ƂŁA��肢�������~�\�̂���\�h���ʂ����߂Ă���悤�ł�
|